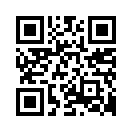2015年05月13日
については
人間を犬派と猫派に分けると、 吾輩は紛れもなく 犬派 である。
その件については、 このブログで 再三再四 宣言したとおりである。
更に、 人間の子どもを 「シートン動物記」派 と 「ファーブル昆虫記」派 に分ければ、
吾輩は 「シートン動物記」派 であったことを 白状せねばなるまい。
近頃は、 無派閥が増えていると推察するが、 子どもというのは、 元来 生き物が好きだ。
否、 好きでなければならぬ。
地球上に生きるのは 人間ばかりではない。
むしろ 人間以外の生き物の方が断然多い。
ひとたび 地上に生を受けたからには、 同じ世界に生きる他の仲間が気になるのは 当たり前の成り行きである。
そうやって、 生き物のなんたるかを学んでいくのである。
であれば、 当然の帰結として、
書籍の分野では、 この 二大派閥 が表層化するはずだ。
「ファーブル昆虫記」で有名なのは、 言わずと知れた フンコロガシ である。
「シートン動物記」で有名なのは、 オオカミ王ロボ だろう。
ロボは 魅力的だ。
どのくらい魅力的かというと、
自分が人間であることを忘れて、 狼の味方になってしまうほどだ。
他にも、 たくさんの動物たちの話がある。
吾輩が読んだのは 小学生の頃だったので、 残念ながら、 詳細はうろ覚えでしかない。
ただ、 面白かったという印象は、 しっかりと残っている。
ほとんどが野生生物の物語だが、
都会の裏町を舞台にした「裏町の野良猫」 という毛色の変わった話もある。
それら たくさんの物語の中に 、「銀の星・あるカラスの話」 というのがあった。
もちろん 主人公は カラスである。
最後は 悲しい結末を迎えるが、 けっこう好きだった。
「カケスは毎日ハードボイルド」のカケスも、 カラスの仲間である。
コンラート・ローレンツの 「ソロモンの指環」にも カラスが出てくる。
コクマルガラス・ズキンガラス・ワタリガラスたちである。
相当に賢い。
人間と暮らすカラスの中には、 言葉をしゃべるようになるのがいる。
インコなどは、 ただ真似るだけで、 意味が分かっている訳ではないらしい。
家に帰った途端に「オカエリ」と言ったとしても、 それは偶然であるという。
だから、 インコに
「バーカ、バーカ、バカヤロウ」とか、
「オオマヌケノ、スットコドッコイ」
とかいわれても 怒ってはならない。
それは 彼らの罪ではない。
どうしても怒りたければ、
言葉を教えた人間を見つけて怒る、 というひと手間をかけるべきだ。
それに対して カラスの仲間は、 人間が使う言葉の意味と全く同じではないにしろ、
どうやら 彼らなりの理解で 、意味を使い分けているらしい。
カラスに言われたら、 気にした方が良い。
ホシガラスは、 山道で 人間の行く先々に現れて、からかう という話も聞いた。
八咫烏(やたがらす)なら、 神武天皇の道案内くらいはするはずある。
ゴミを散らかすせいもあってか、 カラスは 一般に嫌われているようだが、
なかなかに面白い生き物なのだ。
そこいらにいるカラスでさえ 軽く 30年 くらいは生きるらしい。
60年 とか 70年とか生きた という記録もある。 思ったより長生きである。
賢い上に長生きだから、 色々と面白い。
ある日のことである。
家を出て、 駅に向かう道すがら、 ニャーニャーと猫の泣き声が聞こえた。
甘えるような子猫の声である。
捨て猫か? と辺りを見回しても 猫の姿が無い。
そしらぬ様子の カラス がいるばかりである。
そのまま進むと、またもや ニャーッと声がする。
今度は 機嫌の悪そうな猫の声に聞こえた。
しかし、 やはり 猫はいない。
カラスがいる。
ちょっと不思議に思いながら、 尚も進んでいくと、
ニャーオゥという声が、 頭上 から聞こえたのだ。
唖然として見上げれば、 電線にカラスがあーっ!!!
えっ? と思って振り向けば、 通りすがりのカラス が、 ニャーニャーやってるではないか。
カラスたちの間で、 猫の鳴き真似が ブーム だったらしい。
まったく、 何をやってくれるんだか。
「くれないの影」には 「寿々芽」という ふざけた名前のカラスが登場する。
実を言うと、 吾輩はカラスが好きだ。
彼らは、犬の鳴き真似だって、立派にやってくれる。
その件については、 このブログで 再三再四 宣言したとおりである。
更に、 人間の子どもを 「シートン動物記」派 と 「ファーブル昆虫記」派 に分ければ、
吾輩は 「シートン動物記」派 であったことを 白状せねばなるまい。
近頃は、 無派閥が増えていると推察するが、 子どもというのは、 元来 生き物が好きだ。
否、 好きでなければならぬ。
地球上に生きるのは 人間ばかりではない。
むしろ 人間以外の生き物の方が断然多い。
ひとたび 地上に生を受けたからには、 同じ世界に生きる他の仲間が気になるのは 当たり前の成り行きである。
そうやって、 生き物のなんたるかを学んでいくのである。
であれば、 当然の帰結として、
書籍の分野では、 この 二大派閥 が表層化するはずだ。
「ファーブル昆虫記」で有名なのは、 言わずと知れた フンコロガシ である。
「シートン動物記」で有名なのは、 オオカミ王ロボ だろう。
ロボは 魅力的だ。
どのくらい魅力的かというと、
自分が人間であることを忘れて、 狼の味方になってしまうほどだ。
他にも、 たくさんの動物たちの話がある。
吾輩が読んだのは 小学生の頃だったので、 残念ながら、 詳細はうろ覚えでしかない。
ただ、 面白かったという印象は、 しっかりと残っている。
ほとんどが野生生物の物語だが、
都会の裏町を舞台にした「裏町の野良猫」 という毛色の変わった話もある。
それら たくさんの物語の中に 、「銀の星・あるカラスの話」 というのがあった。
もちろん 主人公は カラスである。
最後は 悲しい結末を迎えるが、 けっこう好きだった。
「カケスは毎日ハードボイルド」のカケスも、 カラスの仲間である。
コンラート・ローレンツの 「ソロモンの指環」にも カラスが出てくる。
コクマルガラス・ズキンガラス・ワタリガラスたちである。
相当に賢い。
人間と暮らすカラスの中には、 言葉をしゃべるようになるのがいる。
インコなどは、 ただ真似るだけで、 意味が分かっている訳ではないらしい。
家に帰った途端に「オカエリ」と言ったとしても、 それは偶然であるという。
だから、 インコに
「バーカ、バーカ、バカヤロウ」とか、
「オオマヌケノ、スットコドッコイ」
とかいわれても 怒ってはならない。
それは 彼らの罪ではない。
どうしても怒りたければ、
言葉を教えた人間を見つけて怒る、 というひと手間をかけるべきだ。
それに対して カラスの仲間は、 人間が使う言葉の意味と全く同じではないにしろ、
どうやら 彼らなりの理解で 、意味を使い分けているらしい。
カラスに言われたら、 気にした方が良い。
ホシガラスは、 山道で 人間の行く先々に現れて、からかう という話も聞いた。
八咫烏(やたがらす)なら、 神武天皇の道案内くらいはするはずある。
ゴミを散らかすせいもあってか、 カラスは 一般に嫌われているようだが、
なかなかに面白い生き物なのだ。
そこいらにいるカラスでさえ 軽く 30年 くらいは生きるらしい。
60年 とか 70年とか生きた という記録もある。 思ったより長生きである。
賢い上に長生きだから、 色々と面白い。
ある日のことである。
家を出て、 駅に向かう道すがら、 ニャーニャーと猫の泣き声が聞こえた。
甘えるような子猫の声である。
捨て猫か? と辺りを見回しても 猫の姿が無い。
そしらぬ様子の カラス がいるばかりである。
そのまま進むと、またもや ニャーッと声がする。
今度は 機嫌の悪そうな猫の声に聞こえた。
しかし、 やはり 猫はいない。
カラスがいる。
ちょっと不思議に思いながら、 尚も進んでいくと、
ニャーオゥという声が、 頭上 から聞こえたのだ。
唖然として見上げれば、 電線にカラスがあーっ!!!
えっ? と思って振り向けば、 通りすがりのカラス が、 ニャーニャーやってるではないか。
カラスたちの間で、 猫の鳴き真似が ブーム だったらしい。
まったく、 何をやってくれるんだか。
「くれないの影」には 「寿々芽」という ふざけた名前のカラスが登場する。
実を言うと、 吾輩はカラスが好きだ。
彼らは、犬の鳴き真似だって、立派にやってくれる。
Posted by jiangei at
10:29